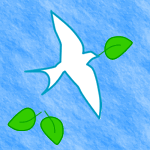› デイサービス「上笠の家」から › まっちゃんの、ふつうな話
› デイサービス「上笠の家」から › まっちゃんの、ふつうな話2014年03月11日
ひなまつり
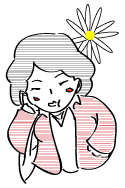
今朝、フロントガラスの上に雪が・・・・
暖かい日差しとともに、雪もあっという間に
溶けて、春を思わせる午後です。
みなさんお元気でお過ごしですか~?
こうほう@まっちゃんです。
先週は、おひな祭りでした。
娘たちも、大人やし、猫が2匹もいることもあって、
ここ数年、ひな人形を出してしていないわが家ですが・・・
先日、市内のギャラリーのひな人形展に行ってきました。
今宿の、アートスペースひらき さんです。

手作りのおひなさま。
着物は「さをり織り」の布でできています。
ひな祭りは、女子のすこやかな成長を祈る節句の年中行事。
いつごろ始まったかは諸説があるようですが、
初めは儀式的なものではなく、「遊びごと」であり、
「ひなあそび」という言葉もうまれました。
平安時代には、川へ紙で作った人形を流す「流し雛」があり、
ひな人形は、「災厄よけ」の「守り雛」として祀られるようになったようです。

これも、手作りのひな人形です。
ひな人形が飾られるようになったのは、江戸時代から。
女子の「人形遊び」と節物の「節句の儀式」と結びつき、
全国に広まったようです。
飾り物であり、一生の災厄をこの人形に身代りさせるという、
祭礼的意味合いも強くなり、武家子女など身分の高い女性の、
嫁入り道具のひとつに数えられるようにもなりました。
なので、だんだん華美になり、より贅沢なものへとなっていったんですね。

江戸時代後期には「有職雛」とよばれる、
宮中の雅びな装束を正確に再現したものが現れ、
さらに今日の雛人形につながる「古今雛」が、
江戸中期には五人囃子人形が現れ、
幕末までには官女・随身・仕丁などの添え人形が考案されました。
嫁入り道具や台所の再現、内裏人形につき従う従者人形たち、
小道具や御殿、壇飾りなど、急速にセットが増え、
特に関西では、スケールの大なものが作られるようになりました。

そういえば、3月3日に、ひな人形をさっさと片付けないと結婚が遅れるとか??
・・・ウチの娘たちがヨメに行かないのはこのためか・・・(汗)
なんていうのは、昭和初期に作られた俗説らしいですよ。
地域よっては、しつけの意味合いで言われているようですが、
旧暦の場合は、梅雨も近いので、早く片付けないと、
湿気てカビがはえたりするという理由から、らしいですよ。
ひな人形は出してないけど、これは作ってます。

ちらし寿司。
お寿司はハレの日の食事ですが、なぜ、ひな祭りにちらし寿司なんでしょうね。
これも、諸説があるようやけど、平安時代のころに、
今のお寿司の原型の「なれ寿司」をお祝いの膳に出したとか。
そこに、季節のもの、菜の花やエビなどを飾り、
華やかなお寿司にして、女の子の幸せを祈ったらしいです。
ちなみに、毎年作ってる「ちらし寿司」やけど、
今年はあるもので作ったので、紅ショウガが切れ、
貝のおすまし汁もなく・・・
手抜き??
いやいや、娘たちの幸せを願う気持ちは一緒ですよ~
むこさん、募集中!!
よろしく~
まっちゃんの、ふつうな話、でした~
2014年02月04日
立春ですね!
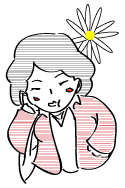
暖かくなったかと思えば、また寒く・・・・
立春を迎えて、春が恋しい今日このごろ
みなさんお元気でお過ごしですか~?
お鍋がおいしい・・・
こうほう@まっちゃんです。
さて、今、守山の第一なぎさ公園の菜の花が見ごろを迎えてます。

これは、カンザキハナナという種類。
約1万2000本の、早咲きの菜の花です。
毎年、早春に、冠雪した比良山系をバックに、
黄色い花を咲かせますね。

先週、行ったときは五分咲きぐらいでしたが、
それでも、たくさんのギャラリーが来てはりましたよ。

今週末には、菜の花フェスタも開催されるとか。
10時~12時、第一なぎさ公園で、菜の花汁、
創作菜の花スィーツの試食販売などがあるそうです。
(なくなり次第終了だそうですよ)
午後からは、JAおうみふじの直売店「おうみんち」で、
菜の花ジェラード、菜の花料理のバイキング、
餅つき、菜の花の佃煮試食会・・なども開催するようです。
ぜひ、行ってみてね~

菜の花畑と、比良山の間に、琵琶湖があります。
5月になると、この琵琶湖岸に自生するハマヒルガオが咲きます。
朝顔のような、かわいいピンクの花です。
そして、7月には、菜の花畑のところに植えられた、
ヒマワリが咲きます。これも見ごたえがありますよ。
さて、今日の「食」ですが・・・・
昨日は節分でしたね!
節分といえば・・・・恵方巻き!!
みなさん、今年の恵方、東北東に向かって、食べましたか~~?
黙って、食べないとあかんのですよぉ~
節分に巻きずしを丸かぶりする風習は、もともと和歌山にあって、
それにならって大阪の船場でやり始めたとか、
いろいろ諸説はありますけど、関西発は確かですね。
海苔業界と寿司屋・・・の陰謀(笑)
これを、「恵方巻き」として全国区にしたのはセブンイレブン。
25年前のことやそうです。
最近は、これに便乗して、いろんなロールものが出てますね!

なんでも、巻けばええっちゅうもんでもいないけど・・・
みなさん、商売上手です!
まっちゃんの、ふつうな話、でした~!
2014年01月16日
勝部の火祭り
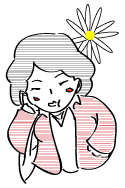
遅ればせながら・・・・
明けましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします。
すっかりお正月太りをしてしまった(涙)、
こうほう@まっちゃんです。
11日、守山・勝部神社の火祭りに行ってきました。
県の無形民俗文化財に選択されている、滋賀県三大火祭りの一つです。

祭りの謂われは、鎌倉時代に土御門天皇が重い病を患った際、
数千年も生きている大蛇がその元凶だというので切り殺して、
火に焼いて踊ったら、天皇の病が全快したことに始まるとか。
切った時、大蛇の胴は勝部神社に 頭は浮気町の住吉神社に落ちたとか。
そこで、勝部神社と住吉神社の二か所で、同じ日に、火祭りが行われています。
大蛇の頭、胴体をそれぞれ、松明に見立てて焼くんですね。

夜、7時前に勝部神社に到着。
道路には、大きな松明が置かれています。
頭の部分はなたね殻です。
町内を巡行した3基の太鼓が8時過ぎに神社前にきて、
太鼓を担いでいた赤と白のふんどし姿の若衆の、
掛け声とともに、境内に太鼓が入ります。

そのあと、若衆はシュウシ棒と呼ばれる白木の棒を、
左肩にかついで本殿前に並び、ここで神職・氏子総代から、
勝部神社の護符を頂き、いよいよ、松明を境内に運びます。
松明の1基の全長は約6m、太さは直径約80cm、
頭につけられた、なたね穀の直径は約400cm、
厚さは約150cm、重さは約450kgだそうです。

境内にはすでに6つの松明が置いてあって、
残りの6基が運び込まれると、いよいよ点火。
点火を担当するのは、今年成人という若者3人。

ちょうど9時前ぐらいに点火され、一気に12基が燃え上がります。
熱い炎のその前で、若衆たちが無病息災を祈願して、
「ごうよ」「ひょうよ」(御悩平癒のこと)と、
大きな掛け声をかけながら乱舞します。


やがて、炎が小さくなり、今度は、引き松明です。
若衆がまだ火が残る松明を引いて、
神社の周囲にある小川に沈めていくんですね。
松明の、火の粉が残っている柴や木を持ち帰って、
その火で朝の粥をたいて食べると、一年中、健康に過ごせるとか。
かまどがない現代でも、ゲンを担いでか、
持ち帰る人が多くいましたよ。

祭りの終焉には、若衆が日除け厄除けのお札を授与、
一般参拝者も、そのお札をいただくことができます。
なんでも気持ちの持ちようですが、燃えるまで2時間待ち、
(カメラの場所取りとか・・・見学者の多いこと~)
燃えるのは、あっという間の、10分ほどです。
でも、お札をいただくと、なんか、ありがた~い気持ちになりますね。
祭り好きとしては、また、機会があれば行きたいですね!
さて、お正月といえば、おせち。
このお正月もおせちを作りましたよ~。
手の甲を痛めていたので、思わぬ時間がかかり(涙)、
手は痛いわ、まどろっこしいわで、ちょっと不本意なデキ・・・

買えばええようなもんですが、おせちに何万円とか、
なんかもったいないような気がして買えず・・・貧乏症です(汗)

でも、お酒は贅沢で・・・(笑)
まっちゃんの、ふつうな話、でした~!
2013年12月09日
近江の秋
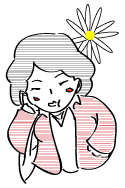
師走です!
朝夕がめっきり冷えてきました!
みなさん、お元気でお過ごしですか?
風邪などひいていませんか?
週に2回は、お鍋・・・という、
こうほう@まっちゃんです。
先日、紅葉で名高い、安土町の「教林坊」に行ってきました。

たまたま、彦根まで行く予定で出かけたのですが、
滋賀県観光情報にある、「紅葉だより」で見かけたのが、この教林坊。
ちょうど、近くまで行ったので、寄ってみました。

ここの寺院は、あの白洲正子さんが、「かくれ里」として紹介したお寺です。
別名石の寺と呼ばれ、聖徳太子が創建したと伝えられています。

中に入ったとたん、目に入ってきたあざやかな紅葉。
めちゃめちゃ、キレイです!




中央の大きな岩は、太子の説法岩。
霊窟があり、聖徳太子自作と言われる石仏があります。

ご本尊の「赤川観音」です。
子宝を授かった村娘の難産を助けたという安産守護の言い伝えがあり、
その時、傍らの小川が安産の血で赤く染まったことから、名づけられました。

書院の前にある庭は、枯れ滝、鶴、亀など巨石を配置した、
桃山様式池泉庭園で、名勝として指定文化財になっています。

普段は、土日しか拝観できませんが、
紅葉の時期は、毎日拝観できて、夜はライトアップもされます。
さて、教林坊をあとに、彦根へ。
ちょっといっぷくは・・・・コメダのコーヒー。
最近、あちこちにできたコメダコーヒー。
名古屋に本部のある有名なコーヒー店ですね。

コメダの名物は、これ!
有名なシロノアール。590円。
温かく甘口のデニッシュの上にソフトクリームを載せた軽食兼デザート。
メープルシロップが添えられていて、好みでかけていただきます。
名前の由来は日本語の白(「シロ」)と、
フランス語で黒を意味する「ノワール」を組み合わせたものとか。
冷えたソフトクリームと温めたデニッシュという対極の組み合わせに、
白と黒をなぞらえて付けられたものなんですって!
まっちゃんの、ふつうな話、でした~
2013年11月19日
紅葉の比叡山
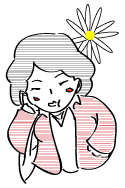
ご無沙汰で~す!
みなさん、お元気でお過ごしですか?
すっかり秋、ですね!
風邪など、ひいていませんか?
こうほう@まっちゃんです。
ご無沙汰理由はいろいろありますが・・・汗
自宅のマイパソコンがダウンし・・・
私が、ん十年ぶりに扁桃腺で熱を出したり・・・
雨降りの駐車場で車止めにけつまづいて転倒、
手の甲の骨にひびが入って全治6週間・・・・
そして、事務所の、私が使ってるパソコンがダウン・・・
どないなってますん・・・涙
と、まぁ、いろいろありましたが、
11月に入って、風邪もひかず元気です!
さて、紅葉だよりが聞こえてきましたが、
先日、比叡山の紅葉をちょっぴり味わってきました!

山頂へは、坂本ケーブルに乗っていきましたよ。

大津市坂本にある、坂本ケーブルの駅です。
これは国の有形登録文化財に指定されています。

改札から、ケーブルカーが見えます。
世界文化遺産である比叡山延暦寺の表参道として、
1927(昭和2)年に敷設されたケーブルは、日本最長の2025m。
山頂の延暦寺駅まで11分で結びます。

ケーブルの車両は二機あって、それぞれ、「縁」と「福」という名前が付いてます。
グリーンの車体のこれは、「縁」号。
途中に駅が二つもあるんですよ~
トンネルも二つあります。

延暦寺駅です。
これがまた、ちょっとステキなんですよね~
坂本駅とはまた違う、大正ロマンを感じる駅舎なんですよ。

ちょっとレトロでいい感じでしょ。
ギャラリーになっている二階は、かつて貴賓室だったとか。
歴代の首相経験者や、かの松下幸之助さんとか、
延暦寺を参詣した著名人の芳名禄が残っているらしい。

延暦寺駅の前にある展望台から見た琵琶湖。
琵琶湖大橋や沖島まで見えます。
ここから、徒歩10分で、延暦寺根本中堂に着きます。

延暦寺は、東塔・西塔・横川にという地域に分かれていて、
それぞれに中心となる仏堂があり、「中堂」と呼んでいます。
この、東塔の根本中堂はその最大の仏堂で、延暦寺の総本堂。
もちろん国宝。ご本尊は薬師如来。
回廊は重要文化財です。

1200年もの間、灯り続けるお灯明「不滅の法灯」が有名ですが、
静寂な中にあるご本尊、薬師如来さんに、思わず手を合わせました~
厄祓い、病祓いのお守りも買ってきましたし~
お昼時やったので、休憩所でもある一隅会館の地下にある、
「鶴喜そば」の看板にひかれ・・・

比叡山そばをいただいてきました!
山菜、天かす・・などが入ってます。780円、かな。
「鶴喜そば」は、坂本の日吉大社の門前にあるおそばやさん。
創業二百九十年らしい。
三塔十六谷、三千坊といわれた比叡山延暦寺。
坂本は、その台所を預かる門前町として栄えた町で、
修行僧や参詣する人々のために作られてきたんですね。
ごちそうさま~!
まっちゃんの、ふつうな話、でした。