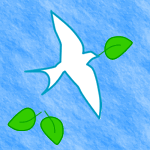› デイサービス「上笠の家」から › 2014年01月
› デイサービス「上笠の家」から › 2014年01月2014年01月16日
勝部の火祭り
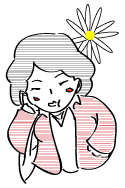
遅ればせながら・・・・
明けましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします。
すっかりお正月太りをしてしまった(涙)、
こうほう@まっちゃんです。
11日、守山・勝部神社の火祭りに行ってきました。
県の無形民俗文化財に選択されている、滋賀県三大火祭りの一つです。

祭りの謂われは、鎌倉時代に土御門天皇が重い病を患った際、
数千年も生きている大蛇がその元凶だというので切り殺して、
火に焼いて踊ったら、天皇の病が全快したことに始まるとか。
切った時、大蛇の胴は勝部神社に 頭は浮気町の住吉神社に落ちたとか。
そこで、勝部神社と住吉神社の二か所で、同じ日に、火祭りが行われています。
大蛇の頭、胴体をそれぞれ、松明に見立てて焼くんですね。

夜、7時前に勝部神社に到着。
道路には、大きな松明が置かれています。
頭の部分はなたね殻です。
町内を巡行した3基の太鼓が8時過ぎに神社前にきて、
太鼓を担いでいた赤と白のふんどし姿の若衆の、
掛け声とともに、境内に太鼓が入ります。

そのあと、若衆はシュウシ棒と呼ばれる白木の棒を、
左肩にかついで本殿前に並び、ここで神職・氏子総代から、
勝部神社の護符を頂き、いよいよ、松明を境内に運びます。
松明の1基の全長は約6m、太さは直径約80cm、
頭につけられた、なたね穀の直径は約400cm、
厚さは約150cm、重さは約450kgだそうです。

境内にはすでに6つの松明が置いてあって、
残りの6基が運び込まれると、いよいよ点火。
点火を担当するのは、今年成人という若者3人。

ちょうど9時前ぐらいに点火され、一気に12基が燃え上がります。
熱い炎のその前で、若衆たちが無病息災を祈願して、
「ごうよ」「ひょうよ」(御悩平癒のこと)と、
大きな掛け声をかけながら乱舞します。


やがて、炎が小さくなり、今度は、引き松明です。
若衆がまだ火が残る松明を引いて、
神社の周囲にある小川に沈めていくんですね。
松明の、火の粉が残っている柴や木を持ち帰って、
その火で朝の粥をたいて食べると、一年中、健康に過ごせるとか。
かまどがない現代でも、ゲンを担いでか、
持ち帰る人が多くいましたよ。

祭りの終焉には、若衆が日除け厄除けのお札を授与、
一般参拝者も、そのお札をいただくことができます。
なんでも気持ちの持ちようですが、燃えるまで2時間待ち、
(カメラの場所取りとか・・・見学者の多いこと~)
燃えるのは、あっという間の、10分ほどです。
でも、お札をいただくと、なんか、ありがた~い気持ちになりますね。
祭り好きとしては、また、機会があれば行きたいですね!
さて、お正月といえば、おせち。
このお正月もおせちを作りましたよ~。
手の甲を痛めていたので、思わぬ時間がかかり(涙)、
手は痛いわ、まどろっこしいわで、ちょっと不本意なデキ・・・

買えばええようなもんですが、おせちに何万円とか、
なんかもったいないような気がして買えず・・・貧乏症です(汗)

でも、お酒は贅沢で・・・(笑)
まっちゃんの、ふつうな話、でした~!