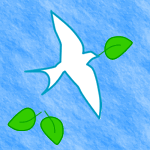› デイサービス「上笠の家」から › まっちゃんの、ふつうな話
› デイサービス「上笠の家」から › まっちゃんの、ふつうな話2015年01月29日
遅ればせながら・・・
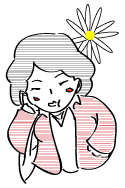
大寒も過ぎ・・・
遅ればせながら・・・・
新年おめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします。
寒い日が続いていますね~
お久しぶりです。
こうほう@まっちゃんです。
インフルエンザも流行ってますが、
みなさんお変わりなくお過ごしでしょうか?
さて、あまりに寒くて、今年は火祭りにも行けず・・・
でも、東和の建築部・リファイン守山の、
「新春家中まるごと大相談会」に行ってきましたよ~

リフォーム相談だけでなく、お楽しみイベントもありました!

お餅つきです!
なかなか、慣れた感じです~

道行く人も、車の人も、ちらっと眺めていきます。

ちびっ子も参加しま~す!

つきあがったら、丸めます~
丸めてるところは写真を撮ってません・・・
なんせ、丸める係やったので~
さてさて、お餅と言えば・・・
「ハレの日」に神様にささげる神聖な食べ物でした。
ハレというのは、晴れ着、晴れ姿とかいうように、
特別の、といいう意味ですね。
お正月にお餅を食べるのは、平安時代に始まったとか。
宮中で健康と長寿を祈願して行われた正月行事「歯固めの儀」に由来。
お餅は長く延びて切れないことから、長寿を願う意味が込められたようです。
そして、神様へのお供え物のお餅をいただくことで、
一年の無病息災を祈る気持ちを込めたんですね。
そうそう、鏡餅の発祥が野洲市って、ご存じ?
大篠原にある、大笹原神社(本殿が国宝!)の中に、
大篠原神社という社がありますが(国の重要文化財)、
別名を「餅の宮」というそうです。
鏡山周辺のこのあたり一帯は、鏡餅の発祥の地ともいわれ、
街道沿いで、この地域でとれる良質のもち米で作った、
「篠原餅」というお餅が売られ、街道を行き交う旅人に人気だったとか。
この良質のもち米に感謝する思いから、
「餅の宮」が建てられたと伝えられています。
篠原餅、どんなお餅やったんでしょうね。
今は、残っていません。
お餅は、お正月だけでなく、結婚式とか、
おめでたい、特別な日に、昔から作られます。
子どもが生まれてもお餅をいただいたし、妊娠して、
腹帯をしたら「はらみ餅」なんていうのもいただきました。
滋賀や京都ではきかないけど、新潟とか、米どころでは、
子どもが1才になると、お餅を背負わす行事もありますね。
昔は、ハレの日だけやったお餅。
今は、いつでも食べられる、幸せなことですね!

この日は、きな粉を付けたあべかわもちに、
あんこを添えて、いただきました~~
ちなみに、あべかわもちの発祥は、静岡県の安倍川沿い。
安倍川岸で、徳川家康が茶店に立ち寄ったとき、
店主がきな粉を安倍川上流で取れる砂金に見立て、
つき立てのお餅にまぶして献上したところ、
家康はこれを大層喜び、「安倍川餅」と名付けたらしいです~
きな粉は砂金・・・・
あべかわ餅って、長寿と金運を祈願したお餅ですね!
まっちゃんの、ふつうな話、でした~!
2014年10月31日
33年ぶりの大祭!
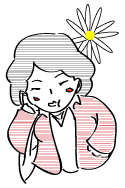
すっかりご無沙汰してしまいました~
すっかり秋です。
街路樹も赤く染まってきました。
みなさま、お元気にお過ごしですか?
季節の変わり目に風邪っぴきの
こうほう@まっちゃんです。
10月も、もう終わりですね。
今月は各地で秋祭りが行われ、祭り好きとしては、
じっとしておれません!
今年は、33年ぶりに開催されるという、竜王町、
苗村(なむら)神社の式年大祭に行ってきました。

苗村神社のりっぱな楼門です。
かつては毎年されてたようですが、33の村があることにちなんで、
33年に一度の開催になったとか。

境内の中は、どこから北の?というくらい大勢の人でにぎわってました。
拝殿と本殿で、神事が行われいました。

ちらっと見えてる屋根が本殿。国宝です!
式年大祭は、33ヵ村の氏子、山車、太鼓が神社に集結し、
山車奉納、踊り奉納、神輿奉納、太鼓奉納などが執り行われます。
三日間開催され、二日目は、神社からお旅所まで渡御があり、
お旅所でも、山車奉納、踊り奉納、神輿奉納、太鼓奉納などが行われます。
二日目も、行ってきました~~

田んぼの中を歩いていきます~
老若男女、たくさんの人が参加し、見物客もあります。

お旅所そばにあるグランドで、
地域ごとに、舞い、お囃子などが奉納されます。

疲れますよね~~
こんな小さな子どもたちも参加します。

人形浄瑠璃もあります。
なんか、ちょっと笑えます~

神楽の奉納もあります。

最後に、ケンケトの舞を披露してくれました。
このケンケトは山之内という地域で、ケンケト祭りとして有名。
男の子たちが、華麗な衣装に身を包み、
長刀を持って舞を披露します。

苗村神社の御祭神の那牟羅彦神(なむらひこのかみ)、
那牟羅姫神(なむらひめのかみ)は、工芸技術や、
産業を伝え広められたとされ、夫婦和合、諸願成就の神様。
そして、國狹槌尊(くにのさつちのみこと)は、国土を開発し、五穀の豊穣と、
財宝の恵み、子守大明神として、幼児子どもを守る神様やそうです。
さて、渡御の長い行列に歩いてついていき、お旅所でちょうとお昼。
地域のお母さん方がお弁当を販売されてました。
「あえんぼグループ」のいなりずしですね。

ちなみに、「あえんぼ」は、山間で咲くつつじのことらしい。
竜王町の町の花、ですね~
それにしても、連日の祭り。
一日中外で太陽の陽を浴びるのって、疲れますね・・・
まっちゃんの、ふつうな話、でした!
2014年07月29日
子どもの成長を願う、「ちまき祭り」
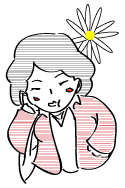
みなさま、暑中お見舞い申し上げます
連日の真夏日、いかがお過ごしですか?
7月も、もうすぐおしまい。
でも、暑さはまだまだ続きそうです~
ビールは、おいしいんですけどね・・・
こうほう@まっちゃんです。
先日、東近江市で全国一の、38度を超える暑さを記録したとか。
その日は、仕事で彦根に行ってたのですが、
彦根でも、37,7度・・・まさに、体温超え。
熱中症で運ばれた人が32人もいたようです。
こんな暑い日が続く中、全国高校野球滋賀県大会は、
決勝戦が行われ、彦根の近江高校が優勝したようですね。
まさに、熱闘! 甲子園でも活躍してほしいですね~
暑いと言えば、6月の中旬、梅雨とは思えない暑さの中、
守山市幸津川(さづがわ)町の、下新川神社で、
子どもたちの成長を祈る、「ちまき祭り」が行われました。

下新川神社は、重要無形民俗文化財に選択されている、
「すしきり祭り」で有名な神社ですが、ちまき祭りはあまり知られてなくて、
見学する人は、ほとんどないですね・・・
名前からして、「ちまき」が、この祭りのメイン!
子どもたちが腰にぶら下げている袋には、
各家で手作りされた「ちまき」が入ってるんですよ~

江戸時代から始まった祭りで、旧暦の端午の節句に、
男の子の祭りとして、ちまき祭りが行われるようになったとか。
男節句とも呼ばれ、男の子の成長を願う祭りやったようです。
女子も参加できるようになったのは、20年ほど前から。
子どもの数が少なくなったためですね。
そして、学校のこともあって、6月の第三日曜日に決められたようです。

神社での神事を終えて、小さなお神輿をかつぎ、
太鼓をたたいて、町内をあるいて回ります。
途中、休憩しながら行くのですが、
その時に、腰にぶらさげた「ちまき」を食べるんです。

このちまき、中に米粉などで作ったおもちが入ってますが、
包んでいる葉っぱは、琵琶湖周辺に自生するヨシ、なんですよ。
熊笹とかはよく見かけるけど、ヨシで包んであるところが、
滋賀県らしいというか、守山らしいというか・・・

神社を出発した、子どもたちの御輿と太鼓。
先頭を、6年生が二人、交代で日の丸の扇を持って、御輿をあおります。
太鼓に合わせて・・・ってあんまり合ってないけど?
「ちょこさー、ちょこさー」
というかけ声をかけて、子どもたちは集落の中を歩きます。
「ちょこさー」は、「いやさか」という意味。
これは・・・・いよいよ栄えること、らしいです。ふ~ん。

地元の会社に、笹につるした「ちまき」を渡して、休憩。
そこでおやつをいただきます。

あと、地元の中州小学校、公民館でも、笹につるした「ちまき」を渡し、
ジュースをもらったりして、休憩。

そして、また、神輿を担いで、神社へと戻ります。
参加した子どもたちは20数人。小学生ばかりですが、
サッカーなどスポーツ少年団とかで試合がある子は、
この日は参加していないのだとか。

子どもたちがおいしそうに食べている「ちまき」ですが、
見学にいった私も、2本、いただきました~
事務所にもどってから、いただきましたよ。
ほんのり甘味があって、なかなかおいしい!
ヨシの葉っぱの香りが、青っぽいけど、それも自然の味ですね。
まだまだ暑い日が続きますが、みなさま、
お体ご自愛くださいますよう~~
まっちゃんの、ふつうな話、でした!
2014年06月09日
お祭り三昧
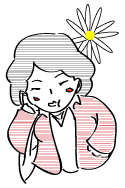
おっと、気づいたら、もう6月!
暑い日があったと思ったら、
梅雨に突入しています。
更新しそびれて、申し訳ないです~
みなさん、いかがお過ごしですか~?
こうほう@まっちゃんです。
5月は、お祭り三昧でした。
祭りがなんで好きかというと、町をあげて祭りに参加する、
そういう体験をしてこなかった、というのもありますが、
祭りが、その町や村の習俗を表すという意味で、興味深いんですね。
今年、5年ぶり、次はいつかわからないという、
余呉の「茶わん祭り」に、行ってきました。
「茶わん祭り」と言っても、陶器市とかではないですよ。
曳山がでる、素朴で個性的なお祭りなんです。
滋賀県には継続されてる曳山の祭りが9つあります。
そのうちの一つが、この「茶わん祭り」。
余呉の上丹生(かみにゅう)という地域の祭礼です。
そのむかし上丹生の陶工が、
技を神から授けられたとして、毎年丹生神社に、
陶器を奉納したのが始まりとされています。

3基の山車(ダシ)があり、木製の素朴な曳山で、
室町時代から伝わる曳幕と、江戸時代から残るつづれ錦の水引幕をつけて、
二ヶ月前から身を清めている工匠が、高さのある山車を作ります。
人形やら陶器でできた壺などを積み上げるんですが、
バランスよく重ねる、この作り方は門外不出の秘伝なんやそうですよ。
曳山の度御の前に、丹生神社で、神事が行われ、
キレイに着飾った子どもたちの稚児の舞の奉納などがあります。

可愛い子どもたちです!
上丹生は100戸ほどの集落なので、子どもたちは、
周辺地域から参加してもらっているそうです。
なので、5年に1回ぐらいしか開催できないんでしょうね。

舞の奉納などのあと、神輿が出て、「茶わんの館」を経て、
御旅所までを、3基の山車と一緒に子どもたちも歩きます。
花笠を持った花奴の舞が道中で披露されます。

山車も、お囃子に合わせて度御します。

積み重ねた飾り物を2本の棒が支えています。

たくさんの見物客が待っているお旅所へ、花奴から入ります。
そのあと、3基の山車が入り、また、子どもたちの舞が奉納されます。

ちょっとわかりづらいですけど・・・
なんせ、初めて行ったので場所取りも難しく・・・
次回は、いつか知らないけど、頑張ります!
舞が終わると、いよいよ、3基の山車の、2本の棒が外されます~
飾り物が、ゆらゆらゆれて、観客から悲鳴も出つつ・・・
ちゃんと、無事に取れるんですよね~!

拍手喝采ですよ~~
奴振りやら稚児の舞、神輿に曳山・・・・
盛りだくさんのお祭りです。
小さな集落に、観光客が9000人。
臨時バスも出てました。
地元の特産やおにぎり、お弁当など、模擬店も出て、
盛り上がってましたね!
さて、祭りと言えば、これですよね!!

サバ寿司。
今年も、茶わん祭りから帰ってから、
寿司めしを作り、お酢に漬けておいたサバで作りました。
まぁまぁ、かな ← 自画自賛、です!
5月4日に、茶わん祭り、翌日5日は、
地元、守山の長刀祭りに行きました。
祭り女子、まっちゃんの、ふつうな話、でした~
2014年04月10日
春です! 桜満開!
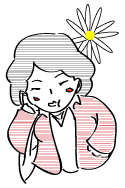
春です!
4月になりました~!
真新しいランドセルの新一年生、かわいいですね!
そこかしこの桜の花も、満開です!
みなさんお元気でお過ごしですか~?
こうほう@まっちゃんです。
早速、野洲川下流、守山市、笠原桜公園の桜を見てきました!

平日の午後でも、そこかしこでお花見をする方たちがいました。
宴会、ですかねぇ~~

野洲川の土手に沿って、約500本のソメイヨシノが植えられていて、
今ちょうど見ごろ。ライトアップもされています。

野洲川の東には、三上山。
右側に、ずらっと桜並木があります。
気持ちの良いところですね~

堤防から、琵琶湖側をみると、こんな感じ。
たくさんの人ですね!
さて、私は、写真を撮りにきたので、
ここで宴会、はなかったのですが、帰りに、
ついつい、こんなのを買ってしまいました!

3色の団子三兄弟、というか、花見団子!
花見団子の始まりは、豊臣秀吉が京都の醍醐で開いた花見が最初とか。
秀吉は日本各地の甘い物を集めたとか言われてますが、
その後、庶民の間でも、花見を楽しむ習慣が広がり、
お団子も、食べるようになったようです。
3色の意味は、桜色はサクラで春を、白は雪で去りゆく冬を、
緑はヨモギで、やがて来る夏を表しているようです。
・・・秋は、ないんかいな?
・・・つまり、あきない、飽きない!
ってことになるらしいですよ。
ほんまかな~(笑)
まっちゃんの、ふつうな話、でした~!