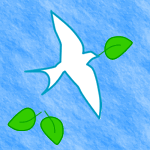› デイサービス「上笠の家」から › 2014年06月
› デイサービス「上笠の家」から › 2014年06月2014年06月09日
お祭り三昧
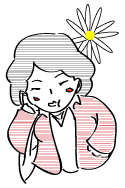
おっと、気づいたら、もう6月!
暑い日があったと思ったら、
梅雨に突入しています。
更新しそびれて、申し訳ないです~
みなさん、いかがお過ごしですか~?
こうほう@まっちゃんです。
5月は、お祭り三昧でした。
祭りがなんで好きかというと、町をあげて祭りに参加する、
そういう体験をしてこなかった、というのもありますが、
祭りが、その町や村の習俗を表すという意味で、興味深いんですね。
今年、5年ぶり、次はいつかわからないという、
余呉の「茶わん祭り」に、行ってきました。
「茶わん祭り」と言っても、陶器市とかではないですよ。
曳山がでる、素朴で個性的なお祭りなんです。
滋賀県には継続されてる曳山の祭りが9つあります。
そのうちの一つが、この「茶わん祭り」。
余呉の上丹生(かみにゅう)という地域の祭礼です。
そのむかし上丹生の陶工が、
技を神から授けられたとして、毎年丹生神社に、
陶器を奉納したのが始まりとされています。

3基の山車(ダシ)があり、木製の素朴な曳山で、
室町時代から伝わる曳幕と、江戸時代から残るつづれ錦の水引幕をつけて、
二ヶ月前から身を清めている工匠が、高さのある山車を作ります。
人形やら陶器でできた壺などを積み上げるんですが、
バランスよく重ねる、この作り方は門外不出の秘伝なんやそうですよ。
曳山の度御の前に、丹生神社で、神事が行われ、
キレイに着飾った子どもたちの稚児の舞の奉納などがあります。

可愛い子どもたちです!
上丹生は100戸ほどの集落なので、子どもたちは、
周辺地域から参加してもらっているそうです。
なので、5年に1回ぐらいしか開催できないんでしょうね。

舞の奉納などのあと、神輿が出て、「茶わんの館」を経て、
御旅所までを、3基の山車と一緒に子どもたちも歩きます。
花笠を持った花奴の舞が道中で披露されます。

山車も、お囃子に合わせて度御します。

積み重ねた飾り物を2本の棒が支えています。

たくさんの見物客が待っているお旅所へ、花奴から入ります。
そのあと、3基の山車が入り、また、子どもたちの舞が奉納されます。

ちょっとわかりづらいですけど・・・
なんせ、初めて行ったので場所取りも難しく・・・
次回は、いつか知らないけど、頑張ります!
舞が終わると、いよいよ、3基の山車の、2本の棒が外されます~
飾り物が、ゆらゆらゆれて、観客から悲鳴も出つつ・・・
ちゃんと、無事に取れるんですよね~!

拍手喝采ですよ~~
奴振りやら稚児の舞、神輿に曳山・・・・
盛りだくさんのお祭りです。
小さな集落に、観光客が9000人。
臨時バスも出てました。
地元の特産やおにぎり、お弁当など、模擬店も出て、
盛り上がってましたね!
さて、祭りと言えば、これですよね!!

サバ寿司。
今年も、茶わん祭りから帰ってから、
寿司めしを作り、お酢に漬けておいたサバで作りました。
まぁまぁ、かな ← 自画自賛、です!
5月4日に、茶わん祭り、翌日5日は、
地元、守山の長刀祭りに行きました。
祭り女子、まっちゃんの、ふつうな話、でした~