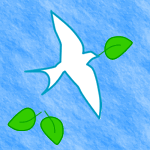› デイサービス「上笠の家」から › 2012年07月
› デイサービス「上笠の家」から › 2012年07月2012年07月31日
夏はロータス!
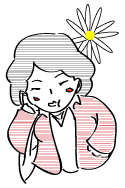
こんにちは~
こうほう@まっちゃんです。
毎日暑いですね~。
みなさん、水分補給、
栄養補給も、忘れないでくださいね。
夏の日差しの中、草津の烏丸半島に行ってきました~

あの世へいった気分にさせる?ハスの群生地ですね。
滋賀県ではヨシ原と一緒に、このハスの群生地も保護条例で守られています。
むやみに、抜いてレンコンを食べよう・・なんて思ったらあきませんよ。
ま、そんな人はいないと思うけど(苦笑)
先週末、このそばにある水生植物公園では、「ハス祭り」があったようです。
原産地はインド亜大陸とその周辺といわれているハス。
地中の地下茎から茎を伸ばし水面に葉を出して、花を咲かせます。
茎に通気のための穴が通っているらしく、大きな葉にお酒を入れて、
茎をストロー代わりにお酒を飲んだりできるそうですよ~
「ハス祭り」では、「像鼻杯」と言って、実際に飲ませてもらえます。→ こちら

烏丸半島のハスの大群落は9.3ヘクタールで、日本でも有数の名所。
7月中旬から8月中頃まで順次花を咲かせます。

ハスの花は、早朝に花が開くというので、
植物園もこの時期は、朝早くから開館してますよ (7時~)
そういえばハスの花が咲くときに、ポンって音がするって?
・・・まことしやかに言われてるけど、
どなたか、聞いたことあります?
そんなん、音って、しませんよね~?
だって、烏丸半島のこれだけのハスが、咲き始めたら、
朝から、ポンポン、ポンポン、・・うるさくてしゃあないですやん・・・
聞いてみたい気もするけど~(笑)
振り向くと、大きくそびえているのが、「夢風車」です。

最近、けなげに回ってますよ~(笑)

ちょっと見づらいけど、現在の発電量が掲示されてました~
頑張ってや~

水生植物公園 みずの森の、花影の池。
炎天下でも、けなげに花は咲くんですねぇ~

ロータス館。
ここでは、ハスやスイレンなど、水生植物についての資料の展示や、
イベントなども行われています。

アトリウム。
熱帯花木や珍しい水生植物などを紹介しています。
ハスといえば、地下茎はレンコンですが、
ハスの実、つまり果実も食べられるそうです。
ロータス館にある、カフェ「ロータス」には、
こんなんもありました~

ハスの実入りラーメン 680円。
ハスの粉を入れた麺と、ハスの実入り。

冷やしハスうどん 700円。
冷たいハスの粉入りおうどんに、ハスの実が入ってます。
今日は、これをいただきました。
ハスの実って、ぎんなんみたいな味、かな。
ついでに、こんなんも食べてきました。

ハス入りソフトクリーム。300円。
コクのあるクリームがおいしい。
ハスの味・・・は、ようわからへん・・・(苦笑)
ソフトクリーム食べて、気分スッキリして、
またもや、炎天下を帰ってきました~~~汗、汗、汗~
まっちゃんの、ふつうな話、でした!
〔DATE〕
草津市立水生植物公園 みずの森
草津市下物町1091番地
夏季期間(7/14~8/15)
開館時間(:午前7時~午後5時(最終入園 午後4時30分)
入場料:大人 300円、高校生・大学生 250円、小中学生 150円
TEL:077-568-2332
FAX:077-568-0955
ホームページは → こちら
2012年07月19日
らくごのはなし
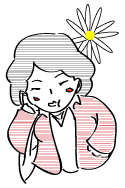
こんにちは~
こうほう@まっちゃんです。
梅雨明けのようですね~。
暑い日差しのなか、
今日も、走ってました~。
週末、「おおなまず寄席」 に行ってきました。

ナニを隠そう、私は大の落語ファンなんです~
大阪の天満天神繁昌亭はもちろん、
地元で開催される落語会とか、いろいろ行ってるんですよ。
今回は、浜大津にある、大津旧公会堂でありました。

京阪電車の線路沿いにある、旧公会堂は、
昭和9年に建設され、名称や用途を様々なに変えながら、
長く、大津市民の交流の場として親しまれています。
その後、施設の老朽化により利用率が著しく低下したけれど、
平成15年から、地域住民を中心に保存運動が起こり、
大津市の中心市街地の賑わいを取り戻そうと整備され、
建築当時の洋館の雰囲気をそのままに、4つの飲食店が入った、
交流・商業施設として大きく生まれ変わりました。
平成22年3月には、景観重要建造物に指定されています。

落語会は、この2階の多目的室でありました。
この日は、60人~80人くらいの人が来てましたよ。
さて、落語は、江戸時代の京都が発祥の地って、ご存知ですか?
新京極にある誓願寺の、安楽庵策伝というお坊さんの、
説教から始まったそうですよ。
人々に仏教の教えを、わかりやすく伝えるのに、
笑い話を加えながら話したようです。
・・・・なるほど、そういや、勉強も同じかも。
面白い先生に習ったことは、今でも覚えてたりしますもんね~
さて、落語に登場する食べ物といえば、
上方落語なら「うどん」、江戸落語なら、「そば」、でしょう。
よく、噺家(はなしか)さんが、扇子をお箸に見立てて、
ズルズル~っと、音を立てて食べるのを見ますね。
上手な噺家さんは、本当に、熱そうに、おいしそうに、
食べはるんですよ~
落語を聞きながら、お腹が鳴ることもありますからねぇ。
というところで、今日の食べ物は・・・・

旧中仙道守山宿、「町家 うの家」にある、
和カフェ 「偲ぶ庵(しのぶあん)」 の茶そば、です。
先日のお休みに行ってきました~!
写真のおそばは、日替わりメニューの、「豚しょうがそば」。
甘酢漬けのしょうがとゆで豚がのった、さっぱりしたおそばです。
デザートが付いて、900円!
おいしかったですよ~
ぜひ、行ってみてくださいね。
まっちゃんの、ふつうな話、でした。
DATE
和カフェ 「偲ぶ庵」
営業時間:11:00~17:30
(ランチタイム 11:00~14:00)
定休日: 毎週火曜日
守山市守山1丁目10-2
077-583-0082
詳しくは→ こちら
2012年07月10日
七夕の話
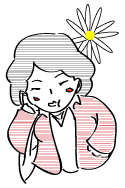
こんにちは~
こうほう@まっちゃんです。
雨がやむと、蒸し暑いですね~。
ぼちぼち、梅雨が明けるんでしょうか。
雨の多いこの時期に、空を見上げました~。
7月7日は、七夕さま。
笹に、願い事を書くというのは、いつから始まったんでしょうねぇ。

これは、とある公民館にあった笹。
たくさんの飾りと、短冊がつるしてありました。
七夕の起こりは、中国から伝わった、"乞巧奠(きっこうでん)"の風俗と、
牽牛(けんぎゅう)と織女(しょくじょ)の伝説で有名な"星祭り"、
それに日本古来の神様に捧げる衣を織る"棚機女(たなばため)"への信仰、
それと、お盆の行事などが結びついたものだといわれています。
”乞巧奠”とは、織姫が巧みな布の織り手であることから、
機織り、裁縫、習字などの技芸の上達を願った行事で、
中国で宮中の女性たちにより起こりました。
これが日本の、短冊に願い事を書く習わしにつながったようです。

公民館の笹につけられた短冊。
「年金減らさないで」 って!(苦笑)
短冊などを笹に飾る風習は、夏越の大祓に設置される茅の輪の、
両脇の笹竹に因んで江戸時代から始まったものらしいです。
6月30日の茅の輪と、つながりがあるんですね~
ちなみに、「たなばたさま」の曲にある”五色の短冊”の五色は、
五行説にあてはめた、緑・紅・黄・白・黒の色らしいです。
こんなふうにして作られた笹を7月6日に飾って、
海岸地域では翌7日未明に海に流すのが一般的な風習やとか。
もちろん、流すとゴミになってしまうので、今、しているところがあるのかどうか。
星祭の伝説は、よく知られている、二つの星の物語です。
こと座のベガは、織姫(織女・しょくじょ)、
わし座のアルタイルを、彦星(牽牛・けんぎゅう)。
織姫は天帝の娘で、機織(はたおり)の上手な働き者。
牛追いの牽牛もまた働き者で、二人は恋に落ちます。
天帝は二人の結婚を認め、めでたく夫婦となるんですけど、
夫婦生活が楽しくて、織姫は機を織らなくなり、
牽牛は牛を追わなくなるんです。
・・・仕事をしなくなるほど、夫婦生活が楽しいって? うらやまし(苦笑)
このため天帝は怒り、二人を天の川を隔てて引き離しますが、
娘をかわいそうに思い、年に1度、7月7日だけ会うことを許します。
天の川にカササギが橋を架けてくれて、二人は会うことができますが、
雨が降ると天の川の水かさが増し、織姫は渡ることができず二人は会えません。
なので、この日に降る雨は、織姫と牽牛が流す涙といわれ、
催涙雨(さいるいう)と呼ばれるそうです。
さて、今年、雨はやんだけど、二人は会えたのかしら~?
そして、七夕の食べ物といえば・・・・そうめん!

夕べの残り物で、ひとりそうめんをしました~
織女は、天の衣の巧みな織り手だったので、
その糸に見立ててそうめんを食べ、
織物の腕が上がるようにと、昔の人は願ったとか。
織物はしませんけど、仕事はうまくいって欲しいと願う・・・
まっちゃんの、ふつうな話、でした!
2012年07月03日
夏越の祓い
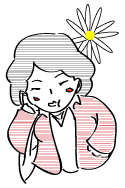
こんにちは~
こうほう@まっちゃんです。
すっごい雨です。よう降ります。
天気予報は、当たりますね~!
そんな梅雨時ですが、先週も走ってきました~
毎年、6月30日は、各地の神社で、
「夏越の祓い」「茅の輪くぐり」が、行われる日なんですよ。

なので、今年は、彦根市にある荒神山神社まで、行ってきました。
写真は、荒神山のふもとにある、荒神山遥排殿。
本社は山の上にありますが、ふもとの拝殿にも、
ススキで作られた、大きな茅の輪がありました。
ここでは、毎年、6月29、30日に、「みなづき祭」が行われ、
29日の夜は、ふもとの拝殿の周辺には夜店が並んで、
たくさんの参拝者であふれるそうです → こちら

そこから、荒神山を周回するように続くアスファルトの道を登ると、
荒神山神社の本社があります。
雅楽が流れる中、社の正面にまわると、大きな茅の輪がありました。

宮司さんに、茅の輪のくぐり方を聞きました。
「左回りに、八の字を描くように、3回くぐる」 ですって。
これをくぐることで、知らず知らずのうちに犯していた?
半年分の穢れを浄化してくれるんやそうです。
そして、残りの半年の無病息災を祈るんですね~
神社によって、人形(ひとがた)に、名前や悪いところを書いて、
水に流すとか、焚き上げる、というところもあるようです。
荒神山神社では、3歳までの子どもさんの代々神楽の奉納もあり、
子どもたちの将来の健康と安全をお祈りすることもできるようです。
帰り道に、近江八幡市の、左義長祭や八幡祭で知られる、
日牟禮神社にも茅の輪があると聞いて、寄ってみました。

拝殿の前に、ありました~
荒神山と同じように、くぐったあと、
写真を撮ってたら、上品なオバサマ方に聞かれました。
「今、くぐってらっしゃったけど、くぐり方があるんですか?」
「左回りに、八の字を描くように3回くぐるんです。
そしたら、半年分の穢れをキレイにしてくれて、
残り半年分の無病息災を祈るらしいです」
荒神山で聞いてきたとおり、プラス、ご利益まで言うと、
めっちゃ、喜んでくださって、みなさんで八の字に、
くぐってはりました~~(笑)
ちなみに、各地の神社で行われる、この「大祓い」は、
年末にも「年越しの祓い」として、同じように、行われるらしいです。
さてさて、この日も、帰り道に買いましたよ・・・・

「水無月」です!!
6月の旧暦名がついおたこの和菓子は、
このへんでもこの時期、よく見かけますね。
京都では、6月30日に食べると良いとされる和菓子なんです。
白いういろう生地に小豆をのせ、三角形に包丁されてます。
上にのった小豆は悪魔払いの意味があり、
三角の形は暑気を払う氷を表しているらしいですよ。
これを食べて、暑さを乗り切ろう!
という意味もこめられてるんですね。
なので、今年も、いただきました~~(笑)
そういえば、荒神山神社の「みなづき祭」には、
山頂の本社で、「水無月」も販売してたらしいです。
さすがに、私が行った二日目には売り切れてましたけどね。
茅の輪をくぐって、カラダもキレイになって?
水無月食べて、暑さも乗り切ります!
まっちゃんの、ふつうな話、でした~