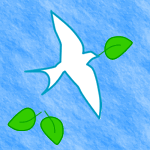› デイサービス「上笠の家」から › 2014年03月
› デイサービス「上笠の家」から › 2014年03月2014年03月11日
ひなまつり
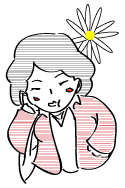
今朝、フロントガラスの上に雪が・・・・
暖かい日差しとともに、雪もあっという間に
溶けて、春を思わせる午後です。
みなさんお元気でお過ごしですか~?
こうほう@まっちゃんです。
先週は、おひな祭りでした。
娘たちも、大人やし、猫が2匹もいることもあって、
ここ数年、ひな人形を出してしていないわが家ですが・・・
先日、市内のギャラリーのひな人形展に行ってきました。
今宿の、アートスペースひらき さんです。

手作りのおひなさま。
着物は「さをり織り」の布でできています。
ひな祭りは、女子のすこやかな成長を祈る節句の年中行事。
いつごろ始まったかは諸説があるようですが、
初めは儀式的なものではなく、「遊びごと」であり、
「ひなあそび」という言葉もうまれました。
平安時代には、川へ紙で作った人形を流す「流し雛」があり、
ひな人形は、「災厄よけ」の「守り雛」として祀られるようになったようです。

これも、手作りのひな人形です。
ひな人形が飾られるようになったのは、江戸時代から。
女子の「人形遊び」と節物の「節句の儀式」と結びつき、
全国に広まったようです。
飾り物であり、一生の災厄をこの人形に身代りさせるという、
祭礼的意味合いも強くなり、武家子女など身分の高い女性の、
嫁入り道具のひとつに数えられるようにもなりました。
なので、だんだん華美になり、より贅沢なものへとなっていったんですね。

江戸時代後期には「有職雛」とよばれる、
宮中の雅びな装束を正確に再現したものが現れ、
さらに今日の雛人形につながる「古今雛」が、
江戸中期には五人囃子人形が現れ、
幕末までには官女・随身・仕丁などの添え人形が考案されました。
嫁入り道具や台所の再現、内裏人形につき従う従者人形たち、
小道具や御殿、壇飾りなど、急速にセットが増え、
特に関西では、スケールの大なものが作られるようになりました。

そういえば、3月3日に、ひな人形をさっさと片付けないと結婚が遅れるとか??
・・・ウチの娘たちがヨメに行かないのはこのためか・・・(汗)
なんていうのは、昭和初期に作られた俗説らしいですよ。
地域よっては、しつけの意味合いで言われているようですが、
旧暦の場合は、梅雨も近いので、早く片付けないと、
湿気てカビがはえたりするという理由から、らしいですよ。
ひな人形は出してないけど、これは作ってます。

ちらし寿司。
お寿司はハレの日の食事ですが、なぜ、ひな祭りにちらし寿司なんでしょうね。
これも、諸説があるようやけど、平安時代のころに、
今のお寿司の原型の「なれ寿司」をお祝いの膳に出したとか。
そこに、季節のもの、菜の花やエビなどを飾り、
華やかなお寿司にして、女の子の幸せを祈ったらしいです。
ちなみに、毎年作ってる「ちらし寿司」やけど、
今年はあるもので作ったので、紅ショウガが切れ、
貝のおすまし汁もなく・・・
手抜き??
いやいや、娘たちの幸せを願う気持ちは一緒ですよ~
むこさん、募集中!!
よろしく~
まっちゃんの、ふつうな話、でした~