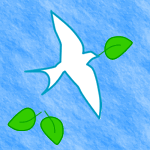› デイサービス「上笠の家」から › 2015年01月
› デイサービス「上笠の家」から › 2015年01月2015年01月29日
遅ればせながら・・・
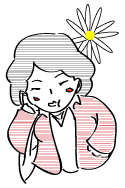
大寒も過ぎ・・・
遅ればせながら・・・・
新年おめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします。
寒い日が続いていますね~
お久しぶりです。
こうほう@まっちゃんです。
インフルエンザも流行ってますが、
みなさんお変わりなくお過ごしでしょうか?
さて、あまりに寒くて、今年は火祭りにも行けず・・・
でも、東和の建築部・リファイン守山の、
「新春家中まるごと大相談会」に行ってきましたよ~

リフォーム相談だけでなく、お楽しみイベントもありました!

お餅つきです!
なかなか、慣れた感じです~

道行く人も、車の人も、ちらっと眺めていきます。

ちびっ子も参加しま~す!

つきあがったら、丸めます~
丸めてるところは写真を撮ってません・・・
なんせ、丸める係やったので~
さてさて、お餅と言えば・・・
「ハレの日」に神様にささげる神聖な食べ物でした。
ハレというのは、晴れ着、晴れ姿とかいうように、
特別の、といいう意味ですね。
お正月にお餅を食べるのは、平安時代に始まったとか。
宮中で健康と長寿を祈願して行われた正月行事「歯固めの儀」に由来。
お餅は長く延びて切れないことから、長寿を願う意味が込められたようです。
そして、神様へのお供え物のお餅をいただくことで、
一年の無病息災を祈る気持ちを込めたんですね。
そうそう、鏡餅の発祥が野洲市って、ご存じ?
大篠原にある、大笹原神社(本殿が国宝!)の中に、
大篠原神社という社がありますが(国の重要文化財)、
別名を「餅の宮」というそうです。
鏡山周辺のこのあたり一帯は、鏡餅の発祥の地ともいわれ、
街道沿いで、この地域でとれる良質のもち米で作った、
「篠原餅」というお餅が売られ、街道を行き交う旅人に人気だったとか。
この良質のもち米に感謝する思いから、
「餅の宮」が建てられたと伝えられています。
篠原餅、どんなお餅やったんでしょうね。
今は、残っていません。
お餅は、お正月だけでなく、結婚式とか、
おめでたい、特別な日に、昔から作られます。
子どもが生まれてもお餅をいただいたし、妊娠して、
腹帯をしたら「はらみ餅」なんていうのもいただきました。
滋賀や京都ではきかないけど、新潟とか、米どころでは、
子どもが1才になると、お餅を背負わす行事もありますね。
昔は、ハレの日だけやったお餅。
今は、いつでも食べられる、幸せなことですね!

この日は、きな粉を付けたあべかわもちに、
あんこを添えて、いただきました~~
ちなみに、あべかわもちの発祥は、静岡県の安倍川沿い。
安倍川岸で、徳川家康が茶店に立ち寄ったとき、
店主がきな粉を安倍川上流で取れる砂金に見立て、
つき立てのお餅にまぶして献上したところ、
家康はこれを大層喜び、「安倍川餅」と名付けたらしいです~
きな粉は砂金・・・・
あべかわ餅って、長寿と金運を祈願したお餅ですね!
まっちゃんの、ふつうな話、でした~!